道場TOP ネタ一覧 コスプレ道場
裕福な家柄の子女が通う小中で過ごした深雪は、同世代の色恋というものを実際に見る機会がなかった。男女交際に開放的ではない校風に加え、全生徒のスターたる美少女の前で「世俗的な」恋愛を見せたがる学生などいなかったからだ。 また、ロマンスを扱うコンテンツを見る趣味も薄かった。退屈で「芸術的な」純愛映画を教養として眺めた程度だろうか。 しかし深雪は、箱入り娘というイメージでもないし、ウブと呼ばれるタイプでもない。むしろ、大人の男女関係に至ることを前提に「恋愛」を捉えているところすらある。

そんな擦れた感性を持つに至ったのは、愛のない結婚をした両親を見て育ったゆえか。深雪は男女の情というものを幼稚だと思う一方で、いかがわしいもの、はしたないもの──汚らわしいものと認識しているきらいがあった。そして彼女を慕った級友たちも、恋愛の価値を低く見積もる深雪に同調する意見を持っていた(学園のアイドルと接するファンとしては、その方が好都合だったからだが)。

深雪にとって恋愛とは、その程度のものにすぎない。だからこそ、自らが達也に捧げる愛情は純粋な「愛」なのだという自負と自信がある。 恋<こい>という言葉は、「乞う」にも通じる、相手を求める行為のこと。足ることを知らない、欲張りな感情だ。でも、私は何も求めない。だから恋ではなく、お兄様を愛している、お兄様の妹として尽くす、ただそれだけ。言うならば、妹としての義務を果たしているにすぎない──。これは本気でそう思っている部分である。

しかし、恋愛感情ではないと思っているのは本人の無知と錯誤ゆえで、彼女の内面は完全に「初恋の女の子」そのままだと言えた。それも一時的なものではなく、恒常的な在り方として、そうなのだ(常時のことゆえに、ますます本人の自覚する機会も失せるのだが)。 たとえば、軽く指が触れ合ったり、肩に手を置かれたりしたときなど。 まるで「告白のできない少女」が、想い人に向けるような反応が彼女の中で生まれる。

思わずスキンシップが発生したときには、飛び上がりそうになる体を理性でおさえつけ──達也の前で「はしたない女の子」である姿など決して見せられないからだ──、喉の奥から出る寸前の悲鳴──嬌声と呼ぶべきか──を寸前で飲み込む努力をしてからでないと達也と目を合わせられない。 そのように、兄との距離が物理的に縮まるにつれ、深雪の体温や心拍数は加速度的に高まってしまう。 達也は護衛任務という意識も優先して、日常的に彼女の肩を抱き寄せるが、そのあいだ深雪はずっと、片想いしている男子に密着されてしまった少女さながらの「緊急警報」が鳴り、「非常事態」に陥っていると言えるだろう。 このまま心臓が爆発して死ぬんじゃないか。 達也への愛をみずから認めるようになれたのが三年前で、その後の深雪は毎日そんな非日常を体験している。それは加速することはあっても醒めることなどはなかった。

ふたりをまるで熟年カップルのよう、と比喩する友人もいるが、それは強気に平静を保っている深雪の表面を見て評しただけのことだ。 三年たっても、深雪は「初恋」のまま変わることのない少女だった。 相思相愛に映るほど仲睦まじいふたりだが、むしろ「初恋」を意識的に処理できない深雪からすれば、いつまでも告白前の、憧れの人をひそかに慕いつづけるような、触れられるだけで身が砕けてしまいそうな、少女らしい初々しさが消えなかった。 彼のために料理を作るときも、セットのマグカップでコーヒーを飲む瞬間も、マッサージの世話をするときも、自分の名を呼ぶ声が耳朶を打つときだって、深雪の胸は高く高く弾む。 締め付けられるように、胸が痛い。 激しすぎる動悸のおかげで、胸が苦しい。 その心理状態を喩えるとしたら、一番イメージしやすいのは、「片想いを秘めながら好きな人に接近されてしまった女の子のよう」、なのだ。 目を閉じればいつだって「初めて好きになったときのこと」が曇りなく思い出せるし、思い出すまでもなく想いが薄れたことなどない。 しかしどんな熱愛カップルであれ、何年も一緒に生活していれば、互いに慣れも生じ、「ときめき」や「憧れ」といった幻想は、現実的な「愛着」「尊敬」へと置き換わっていく。その変化が訪れる期間は、早ければ数ヶ月もかからないし、長くもって三年が限界だという。しだいに「恋人」が「家族」へ、「他人」が「自分の生活の一部」へと上書きされていくということだ。 ひとつの恋心を新鮮なまま長く保つのは、人間という動物の本能からすれば脳の機能的に困難であるそうだ。 それゆえに、恋多き人種にとっては浮気が絶えない原因となるし、逆に恋に焦がれない人種にとっては伴侶との良好な関係を築く秘訣にもなる。それが自然な本能なのだとすれば。 だとすれば、深雪の持つときめきはあきらかに人間の本能を超えている。 兄と一緒に暮らして、生活をともにするようになっても、達也は想いつづけることに値する男性だった。恋という、花火<スパーク>のように不安定な幻想が、やがて安定期に入るはずの自然法則とは無縁だった三年間。 これは過負荷に耐えられず、脳細胞が焼き切れていてもおかしくないのではないか……。

深雪自身がそう内省するきっかけなどは現状において存在しないのだが、もしも自分の心理状態を客観的に観察することになったとしたら、そう懸念を抱くのも当然の状態といえた。 このような感情のかたちは、奇跡と言えるかもしれない。 ──常軌を逸したブラコン。多くの友人たちは、その行き過ぎた慕い方を見た上でこう呼ぶが、評価としてはまったくにおいて正しいだろう。 ただし、肉親への愛情を越えている、という意味での非常軌ではない。「恋心の不変性」という点で、彼女の心は本能のタガから外れている。 妹として愛し、妹として愛されつづければつづけるほど、処理のできないときめきが彼女の胸の中で高まりつづけ、止むことがない。 ……ちなみに達也はというと、どうやら血行や新陳代謝がいいようだな、くらいにこの状態を認識しているから始末におけない。 もちろん、時々テンションが変に上がったり、耳まで真っ赤になるほど紅潮するのは異常かな、とは感じている。妹がさりげなく押し付けてくる胸ごしに伝わる動悸が、不自然に激しいことも知っている。しかし、優等生の妹は「それ以上のボロは出さない」ことに長けすぎているとも言えた。 ボロを隠すどころか、さまざまな自己暗示の結果だろうか、兄のおかげで高揚しているときこそ、彼女は最大のパフォーマンスを発揮できるように自らの内面を「調整」できていた。 頭が真っ白になって何も考えられなくなるような恍惚状態から、その胸の高鳴りを、陶然としながらも前に進むエネルギーへと変えるすべをいつのまにか身に付けていた。 彼女にとり、兄から受け取るものは全てが「恵み」なのだから、糧にならないはずがない。そんな意志と思考に裏付けられたエネルギー回路だった。 妹への愛だけが「通常」でいられる達也に対して、深雪の場合は、兄への慕情だけが「異常」を通過しているという点で、似つつも非対称的な関係かもしれない。 そして、つける薬がどこにも見当たらない関係でもあった。 これは恋だ、という認識をしていない深雪であっても、自分がなにかの病状を患っている気はしている(それはつまり、重症の恋患いなのだが)。 ……でも今はまだ、この病を癒すときではなく。 いつまでもこの高鳴りを、あなたのそばで感じていたい。 いつの日か、お兄様に私の全てを捧げることになってからも、この想いのままでいたい。深雪が自分の「病気」に対して願うのは、そのたったひとつだけだった。

ブログ? そんなの必要ありません! 今日から、いきなりアフィリエイトスタート!
【まにあ道アフィリエイト】まにあ道ならAmazonアソシエイトIDを利用してネタを書くだけで、お気軽に始めていただけます。

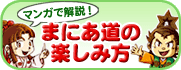


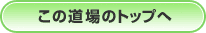
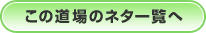







 シュリのおすすめネタ
シュリのおすすめネタ
コメントはまだありません。