道場TOP ネタ一覧 秘密花園道場
子供のための絵本を古書店やバザーなどで物色していると、すぐ隣に児童書コーナーがあることに気づきます。私は児童書をあまり読んだ記憶がないので、投げ売りのような価格になっているそれらが新鮮で、新しい狩場を見つけたような気分です。これから子供をだしにして狩猟本能を未開拓の児童書に向けられると思うと変な笑いが出てくる。子供のためという大義名分があるので財布の紐も緩くなりがち。
そんな中、バーネットの『秘密の花園』を読み返す機会がありました。この本は小学生のころに子供用ダイジェスト版を読み、その後新潮文庫で読み直したのですが、三度目に手に取ってみたところ、今になって新鮮に感じ、思わず涙腺が緩む場面もあり驚きました。
さまざまな媒体で紹介されている評価の高い作品ですので(発表当時は『小公子』『小公女』を超えるものとは思われていなかったようですが)原作を読まなくてもあらすじはよく知られていると思います。英国領インドで孤児になった少女メアリーは、英国ヨークシャーの叔父の屋敷に引き取られ、そこで閉鎖された庭園を見つける。病弱でふさぎ込んでいた従兄弟のコリン、地元の農家の息子ディコンと出会い、三人でその庭を手入れする。元気になったコリンは、父親にその姿を見せ、感動させる。簡単に言ってしまえば、これだけの話です。しかし、読み直していると、細部に味わい深い場面があることに気が付きました。
(文中の原作からの引用は全て、瀧口直太郎さんの訳された新潮文庫版に拠っています)
- わたしとヘビのほかには、誰もいないみたい
この物語は異様な静けさの中からスタートします。ある朝、目を覚ましたメアリーは、広い屋敷の中に自分以外の人間がいないことに気が付きます。両親と使用人はコレラで亡くなり、残った使用人も逃げてしまっていたのです。誰も、メアリーのことを思い出さず、屋敷に残されてしまった9歳の少女。これは異常事態です。しかし、メアリーは心細さも恐怖も感じていません。世話をしてくれる召使が誰もいないことに腹を立てはしても、自分が孤独であることすら気付いていないのです。
メアリーは英国領インドに派遣された英軍士官の父と、美しい母の間に生まれた一人娘です。母親は社交に夢中で、「小さな女の子など欲しくなかった」ので、世話はすべてインド人の召使に任せ、乳母はなるべくメアリーを人目につかぬように、「病弱で気難しい、みっともない赤ん坊」が泣いて奥様をうるさがらせぬように、何でも赤ん坊の望むようにしていました。母親の育児放棄と、メアリーの癇癪を恐れて恭順な姿勢をとりつづける召使により、メアリーは自分と温かなつながりをもってくれる存在がいないままに育っていったのです。コレラの猛威にさらされた屋敷では、彼女は誰からも思い出されず、両親が彼女を案じた形跡もありません。メアリーは既に「たった一人」の世界で生きていたので、屋敷に一人残されても、孤独を感じなかったのでしょう。
やがて、父親の同僚が屋敷を見回りに来た際に、メアリーは発見され、現地の英国人牧師にとりあえず保護されます。その後、英国の叔父のもとに引き取られることになります。
叔父の屋敷の敷地を散策している中で、メアリーは一羽の駒鳥がさえずっているのを見つけます。偏屈な老庭師ベンにそれは「自分がひとりぼっちだっていうことをちゃんと知っていた」鳥だと教えてもらう。彼女は「あたしもひとりぼっちなのよ」と話しかけます。この瞬間、生まれて初めて孤独を自覚するのです。
- メアリーの分身
メアリーは、若いメイドのマーサとの会話の中から、閉鎖された庭の存在を知ります。庭園が閉じられてから10年の歳月が流れています。そしてインドで9歳だったメアリーは、長い船旅で英国にやってきたおり、この時点で10歳程度だと思われます。この閉鎖された秘密の庭は、メアリーと非常に近い存在です。
「だれのものでもないの。だれもそれをほしがらないし、だれもかまってはやらないし、だれもそこへは入って行かない花園なの。たぶんそのなかのものはもうみんな死んでいるんでしょうーーあたしにはよくわからないけど……」
後にディコンに対してメアリーは秘密の花園をこう評します。これは、誰にも見つめられず、10年も捨てられてきたメアリー自身のことでしょう。
作中には、この庭だけでなく、メアリーの魂の分身、一面だと思われる登場人物がいます。ひとりは偏屈な老庭師ベン・ウェザースタッフです。皮肉屋で駒鳥以外は友達はいないようです。
「あんたとわしとはなかなかよう似てるだ。わしらはおんなじ糸で織った布みたいによく似てるだ。わしらはどっちもきりょうがよくねえし、どっちもおんなじくれえ苦虫かみつぶしたような顔してるだ。わしらは二人ともまったくおんなじような、いやな気性の人間だよ」
屋敷の家政婦 メドロック夫人も「あなたはまるでおとしよりみたい」とメアリーを評していますし、マーサも「あんたは妙に年よりみたいなひとだね」と語るシーンがあります。老人ベンはメアリーの分身であり、メアリー同様の不機嫌で怒りを抱えた者です。そして後に秘密の花園の守り手ともなります。
もうひとりは、メアリーの従兄弟であるコリンです。屋敷で存在を隠されていたコリンは、メアリーと出会ってお喋りに興じるようになりますが、なにかにつけて「自分は病気で死ぬんだ」とまるで病気であることを特権であるかのように振りかざします。そして周囲を怯えさせるほどのひどい癇癪もちで、屋敷の人々はコリンに癇癪を起させないように機嫌をとることが最大の任務です。メアリーとそっくりな性質のコリン。作中で、彼が自分の足で立つようになってから、メアリーの描写は極端に少なくなり、コリンの気持ちに関してクローズアップされていきます。メアリーの分身であるコリンは、メアリーと共に蘇った秘密の庭で健やかさを取り戻し、ラストシーンでは、孤独な屋敷の主人である父親の胸に飛び込んでいく。屋敷と庭と人々の再生を印象付ける場面での主役はコリンです。メアリーとその分身達は、一旦は孤立し輝きを失っていましたが、秘密の花園の復活と同じタイミングで再生するのです。
- 屋敷の中でみつめる動物
屋敷の「中」でメアリーが見つめる小さな動物たちは、メアリーと庭の生命力の回復を表現しています。コレラの蔓延で人々が死に絶え、または逃げ去って行った屋敷において、生き残ったメアリーが静けさの中で出会ったのは、たった一匹の、小さな害のないヘビでした。宝石のような目でじっとメアリーをみつめるヘビ(おそらく、この少女をじっと見つめてくれる存在はこれまでいなかったのだと思われます)。ヘビと見つめあうメアリーは、どこかヘビとの親和性も感じさせます。冷血動物(変温動物)であるヘビは、優しい気持ちのない生き物だというイメージがあるからでしょうか。
英国に渡ったメアリーの心身は少しずつ健やかに育ち始めるのですが、その時期に屋敷の探索をしていた少女が出会ったのは、象牙でできた小さな象の置物と、クッションの中に巣をつくったネズミの赤ん坊でした。象牙の象はインドで育ったメアリーにとってはよく知ったものであり、かなり長い時間それで遊びます。まるで孤独だったインド時代の自分自身と遊んであげているかのようです。その後、小さな仔ネズミに対して「もしこんなにびっくりしさえしなければ、これをみんなあたしの部屋へもって帰るんだけど……」と呟くメアリー。小さいけれども、確かに温かい生物が、屋敷に巣を作っていることが発見できました。
そして庭の再生が進んだ頃には、ついに、ディコンの連れて歩くカラスの黒助、りすの栗坊と殻坊、生まれたての仔羊を屋敷の中に招き入れます。メアリーが屋敷の中で出会う動物は、どんどん温かく大きなものになっていくのです。
- 三人の母親
この物語には三人の印象的な母親が登場します。ひとりはメアリーの母である「奥様(メム・サーブイ)」です。とても美しい人で、「レースだらけ」の服を着ており、パーティーに行って楽しく過ごすことだけが大好き。作中ではたびたび、母親はとても美しかったのに娘のメアリーはなんて不器量なんだろうと、容貌の比較のために引き合いに出されます。
もうひとりはコリンの母であるクレイヴン夫人です。若く美しく花の好きな奥様。彼女は既に空の上を居場所とする故人です。「青い空」は彼女を象徴しています、
「奥様はえらく花が好きだっただ―ほんとにお好きだっただよ。奥様は、いつも青空の方へ顔をむけて咲いている花が好きだって、よくいわっしゃったものだ。(略)奥様は青空がただもうほんとにお好きだったが、青空はいつもとても楽しそうに見えるっていわっしゃっただ」
そして三人目は、ディコンとマーサの「おっかさん」であるスーザン・サワビーです。メアリーと出会う前から、メアリーの境遇に心を痛めてマーサを通して助言をし、メドロック夫人に働きかけ、屋敷の主人にして領主であるクレイヴン氏にも話をし、メアリーに関心を持ってもらうよう仕向けていました。野性味あふれる息子のディコンはムアの動物のことなら何でも知っており、生命力あふれた少年です。娘のマーサもメアリーの健やかな生活のために尽力します(彼女は、初めて登場するシーンで暖炉の手入れをしています。これは、メアリーを温める存在であることを示唆しているように読めるのです)。土俗的な母性の象徴であり、ムアの生命力の体現者でもあるスーザン・サワビーは、その子供たちと共に、屋敷と庭とそれに関わる人々に大地の温かさを運ぶのです。初めてであった時にコリンは「あなたにあいたかった」と言い、彼女はそんなコリンを若様ではなく「かわいい坊や」と呼びます。おもしろいのは、この時、スーザンが着ているのは「青いマント」なのです。コリンを抱きしめるスーザンの背景に、青い空の住人であるクレイヴン夫人が重なるかのように感じられます。
- 意外性のある登場人物の配置
再読してみて、随分と印象が変わった登場人物がいます。屋敷につとめるメドロック夫人です。メアリーを通してみるメドロック夫人は、厳格でそのくせに面倒くさがりで、あまり良き大人とは言えませんでした。
しかし、そんなメドロック夫人は、ディコンとマーサの母スーザン・サワビーの幼馴染という面を持っています。小学生時代の同級生であるスーザンに関して、自分の主人であるクレイヴン氏に「健全な心の持ち主」と紹介し、彼女の子供たちも「しごく丈夫でいい子ばかり」と評します。友人であるスーザンが褒められるとニコニコと笑って喜び、彼女との素晴らしい思い出話を語りだすのです。友人を自慢げに語るメドロック夫人は、まるで別人のように生き生きとしており、冷たさは全く感じさせません。メアリーの目からだけでは見えてこない登場人物の一面です。
もうひとり、看護婦(師)という脇役も、再読時に驚くくらい印象の変わった人物です。この看護婦は病人の世話をするのが嫌で、すぐにさぼろうとします。メアリーも「どうしても好きになれなかった」と感じていますし、物語を動かく役目でもない脇役の中でも随分と地味な存在です。
メアリーが庭仕事が忙しくてコリンの部屋にいけなかった際に、コリンは機嫌を損ね、ようやっと部屋に訪ねてきたメアリーと口げんかを始めます。「おまえは、わがままものだ!」「あんたはあたしよりもっとわがままよ」と激しくぶつかります。子供の頃は仲違いした二人にハラハラしていた記憶があるのですが、おとなになってから読むと、子供二人が大騒ぎしている、随分とへんてこな場面です。そして、そのおかしさを感じる読者の気持ちに沿うかのように、看護婦が「ハンケチを口にあてて立ったまま、くすくす笑っている」のです。ああいうわがままな子供には、同じくらいの駄々っ子が向かって行ってくれるといいのだと。
その後、晩にコリンが癇癪を起して大騒ぎをします。悲鳴を上げて泣く声をきいているうちに、メアリーは腹が立ってきて、自分の短気は棚に上げて、こっちも大声で泣いて怖がらせてやるんだと足を踏み鳴らします。この時も看護婦は喜んで「行って坊ちゃんを叱ってあげてくださいな」と応援します。この看護婦の言うことは、大人の読者の気持ちにピッタリなのです。
このように、子供向けのダイジェスト版では味わいきれなかった細部には、この作品の醍醐味がつまっています。まだまだ読むたびに発見があることでしょう。名作を読むとき、いつでも私たちは鮮やかな「秘密の花園」に足を踏み入れることができるのです。
ブログ? そんなの必要ありません! 今日から、いきなりアフィリエイトスタート!
【まにあ道アフィリエイト】まにあ道ならAmazonアソシエイトIDを利用してネタを書くだけで、お気軽に始めていただけます。

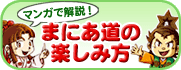
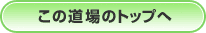
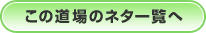







 シュリのおすすめネタ
シュリのおすすめネタ
コメントはまだありません。